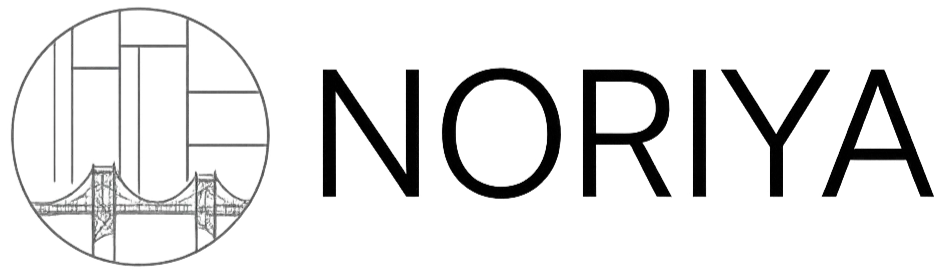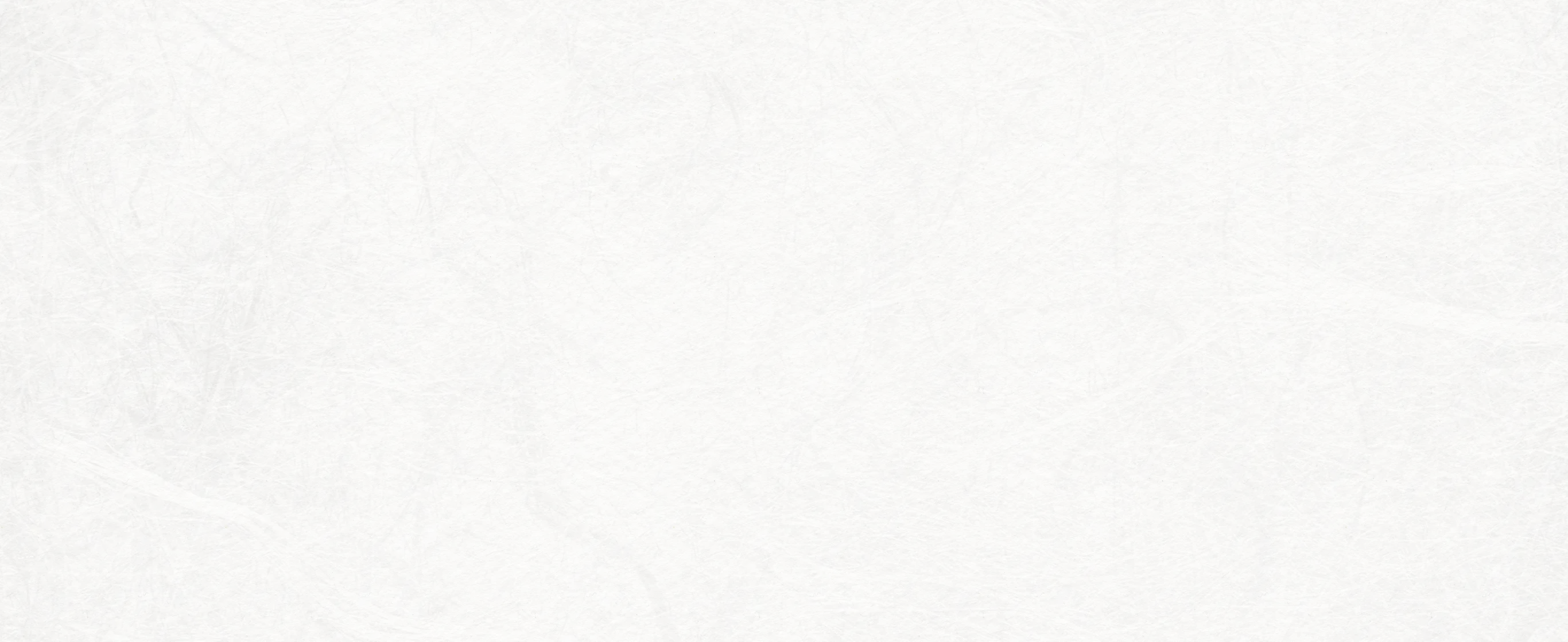海苔がどのように海で育てられているのか、ご存じですか?
普段は手巻き寿司やおにぎりに欠かせない存在として親しまれている海苔ですが、その育てられ方を知っている人は意外と少ないものです。
特に「明石海苔」は、豊かな自然環境と人の技術が見事に融合して作られる特別な海苔として、多くの食通や料理人からも高く評価されています。
ここでは、種付けから収穫、加工までの一連の流れをわかりやすくご紹介します。
◆明石海苔はすべて「養殖」

明石海苔は、完全に養殖によって育てられています。
かつては天然の岩場に自生する海苔も採れていましたが、環境の変化や海域の制限などによって、現在ではほとんど姿を消してしまいました。
実際に、日本全国で流通している海苔のうち、99%以上が養殖品となっています。
ただ、「養殖」と聞くと大量生産のイメージを抱く方も多いかもしれません。
しかし、明石海苔の養殖は機械的に作られるものではなく、漁師の経験と勘を頼りにした繊細な仕事の積み重ねによりできています。
潮の満ち引きや気温の変化、風向き、海の透明度など、自然条件は常に変化しています。
その中で最適な環境を見極め、丁寧に育てていくことで、香り高く質の良い海苔が仕上がるのです。
◆明石海苔の養殖の流れ
① 種付け(10月ごろ)
海苔の一生は「胞子(たね)」から始まります。
専用の網に胞子を付着させる作業が「種付け」で、これは陸上に設けられた施設で行われます。
ここで作られる網は「種網(たねあみ)」と呼ばれ、後に海へと移されます。
この時期の天候や水温管理が、その年の海苔の出来を大きく左右するため、漁師たちは細心の注意を払っています。
② 海に設置(11月ごろ)
種付けを終えた網は、いよいよ明石の海へ設置されます。
養殖方法には大きく分けて「支柱式」と「浮き流し式」の2種類があります。
- 支柱式養殖
海底に支柱を立て、その間に網を張る方法。
潮の干満によって網が水中から現れ、空気や日光に触れることができることにより海苔は光合成を行い、香り高く色つやの良い仕上がりになります。 - 浮き流し式養殖
浮きを用いて網を海面に漂わせる方法。
波に揺られながら成長するため、柔らかく食感の良い海苔に育ちます。
漁場やその年の海の状態に合わせて使い分けられるこの2つの方法は、それぞれに個性ある風味を生み出します。
③ 成長(12月〜2月)
海苔は寒さに強い植物で、特に冬の冷たい海水が成長に適しています。
瀬戸内海の中でも明石の海は、潮の流れが複雑でありながらも穏やかで、豊富な栄養を含んでいます。
また、大きな干満差があることも特徴で、この環境が海苔に独特の旨みと香りを与えます。
海苔は毎日少しずつ成長し、自然と人の手の両方に見守られながら育っていきます。
④ 収穫(12月〜3月)
収穫の時期を迎えると、漁師たちは早朝から船を出し、設置した網を一枚ずつ引き上げます。
網にびっしりと付いた海苔は、刈り取り機で丁寧に収穫されます。
1枚の網からは数回にわたって収穫することが可能で、中でも最初に摘み取られる「一番摘み」は特に柔らかく、風味と香りが格別とされています。
⑤ 加工・乾燥
収穫された海苔はすぐに加工場へ運ばれます。
海苔は時間が経つと風味が落ちるため、鮮度の保持が重要です。
加工場では、まず海苔を洗浄して砂や不純物を取り除き、その後細かく刻んで水と混ぜ、和紙を漉くように一枚ずつ成形します。
乾燥させることで、私たちが普段目にする黒く光る板海苔へと仕上がります。
この工程は手間がかかり、わずかな調整が味や食感に直結します。
◆漁師の経験と技が支える品質
明石海苔の品質は、自然環境だけでなく漁師の判断力と経験によって支えられています。
潮の流れ、気温、海水の透明度、光の強さなどを日々読み取り、最適なタイミングで収穫や加工を行います。
熟練の技によって、毎年最高の状態で仕上がる海苔。それが「明石海苔」の魅力です。
◆ 食卓に届くまで

手巻き寿司やおにぎりに使われる海苔。
普段は何気なく使っていますが、その一枚がどんな環境で、誰の手によって、どれだけの手間をかけて育てられたかを知ると、より深く味わうことができます。
「黒い海の宝石」と称される明石海苔は、自然の恵みと人の技術が融合してできた、まさに“海の手仕事”です。
◆まとめ
明石海苔は、豊かな自然と地域の人々の手によって育てられる、大切な特産品です。
その一枚には、海の恵みだけでなく、漁師たちの知恵や努力も込められています。
食卓に並ぶ明石海苔を、ぜひじっくり味わってみてください。